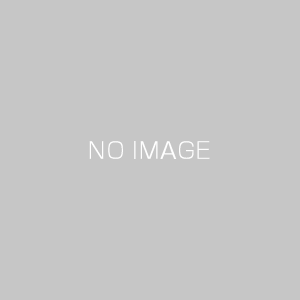「空手」は奥の深い武道
「空手」には色々な流派があり、流派以外にも各教室・道場の個性が強く出る武道でもあります。
習い事として「空手」を選ぶときには、たいていの方は「実用的だろうか」とか、「最強の空手はどれだろうか」ということが気になるのではないでしょうか。
しかし私は、これは教室選びにあたって重要なことではないと自分の経験から感じています。
「黒帯は強いの?」
「どの流派が実践的なの?」
という質問はよく聞きますが、教室選びには全く関係ないことだと私は考えています。
本記事では、空手を習う意味、本当に大切な教室選びの観点をお伝えします。
大切なことは下記の3点です。
・フルコンタクトにするかどうか?
・道場との距離と稽古スケジュールが自分に合うか?
・教室の雰囲気が自分にあうか?
目次
3つの「大事なこと」
インターネットで、空手関係の検索傾向を見ると、「空手」をやっている人が関心を持っている場合と、「空手」を習おうかなという関心を持っている場合の2通りがあります。
特定の選手の名前が検索されているケースなどは、空手関係者でしょう。
「オリンピック」や「帯」について検索している人は、実際に「空手」を稽古している人ではなくて、少し関心があるというケースが多いと思います。
これから「空手」を習おうかな、という人は、どうも「最強」「実践」「黒帯」などのキーワードに関心を持たれているようですが、ここで個人的な意見ではありますがあえて書きますね。
「最強」「実践」「黒帯」の強さは、空手の教室選びではまったく考える必要はありません!
確かに空手の「黒帯」はどんな流派でもそう簡単には取得できません。
黒帯の人は概ね一般人では適わないだけの力量を備えています。
そんなとてつもなく強い人たちが戦ったらどうなるのか?
どの流派が「最強」なのか「実践的」なのか?
気になる気持ちはよくわかります。
しかし空手を習う際には、空手の連盟や流派による強さの違いと、自分が何を学びたいのかを、分けて考える必要があります。
フルコンタクトにするかどうか
常々私は、「フルコンタクト」と「寸止め」との間に優劣はないと伝えていますが、この意見には多くの反対の声もあります。
ですが、教室選びにあたっては「フルコンタクト」の空手を自分のライフスタイルに取り入れるかどうかという点は必ず検討してください。
というのは、フルコンタクト空手系統の空手は拳や身体の強さを鍛えることが避けられず、どうしても身体にかかる負荷が大きいからです。
流派によってはかなり高度な防具も導入していますが、それでも基本的に身体で打撃を受けることが多くなるため、多少なりともあざができることもあり、手や足に怪我をする率も高くなっています。
何よりも手拳を痛めないために拳を鍛えるので、個人差はありますが、指の関節などが少し黒ずんでいく傾向があります。
特に女性にとっては、「手を鍛える」「青あざができる」という点に抵抗があるかもしれません。
そういう場合にはフルコンタクトの空手はお勧めできません。
稽古の違いは、体格の違いにも現れます。
極真系(フルコンタクト、防具なし)の人と、松濤館流(伝統派、寸止め)の人では、体格が全然違うのです。
前者は筋肉質で、しっかりとした体格の人が多い傾向があり、後者は線は細くても芯が通った体格の人が多い傾向があります。
道場へのアクセスとスケジュール
次に挙げたいのが、道場へのアクセスのしやすさについてです。
当たり前と言えばあたりまえのことなのですが、生涯を空手の修行に費やす、というのでなければ、どんなに立派な師匠がいる道場を見つけても、遠隔地であったならば練習に行くことはできません。
江戸時代の剣客ならいざ知らず、住み込みで師匠の道場で修行することはできませんし、また、必要でもないでしょう。
社会人ならば仕事があり、家庭もありますね。
子どもなら、学校や自宅や塾での勉強があり、また、自分で移動できる距離に限界があります。
中高生ならばその時期にしかできない勉強に恋に課外活動にと忙しく、また、お金があるとは限りません。
そういった諸々の事情を考えると、「無理なく通える場所にある」「自分の余暇時間に稽古スケジュールが組める」ということは必須条件なのです。
サッカーやバスケットボールでもそうだと思いますが、週一回の練習と、週三回の練習では進捗に大きな差がありますよね。
ましてや、稽古が一か月に一回になってしまったら、ほとんど上達しないといってもいいでしょう。
今は大体、どの流派、どの道場でも帯は5色くらいあり、習熟度に応じて帯が上がっていくのでモチベーションを維持してくれます。
週2回から3回位のペースで練習して半年ほどで昇級審査が受けられるというのが通常ですので、白帯から始まり、黒帯まではおおよそ3年くらいはかかります。
黒帯までとるかどうかは、時間的な都合が合うかどうかや、個人的にどこまでやりたいと思うか次第だと思いますが、いずれにしても、往路だけでも1時間あるような道場を選んでしまったら、稽古に通うだけでとんでもない時間がかかってしまいます。
教室を選ぶときは、下記の3点を意識して選ぶことを強くお勧めします。
・自分の家から近いか?
・学校や職場から近いか?
・学校や職場と自宅との?通学路か通勤路上に道場があるか
稽古スケジュールもしっかりと確認しておいてくださいね。
大人でも子どもでも、練習を休むと身体は自然と負荷の低い状態に戻ろうとするため、どうしても稽古に行くことを苦痛に感じてしまいます。
あまり長い時間稽古できないでいると、道場に行くのが次第におっくうになってしまうため、結果的に長続きしなくなってしまいます。
「生兵法は大怪我の基」と言いますが、「空手」の稽古を途中でやめてしまうと、自分の力量を見誤ってしまい、かえって危ない目に合うことも考えられます。
黒帯までとは言わずとも、「空手」を通じて人生を豊かにするためには、2年か3年は続けたいものです。
そう考えると、道場が通いやすい場所にあるというのはとても大切なことなのです。
教室の雰囲気が自分に合うか
私は道場選びにあたっては、まず道場を訪れて体験することを勧めています。
それは、道場を訪れたときの感覚を大切にしてほしいからです。
「あれ?なんか変だな」と感じたら、迷う必要はありません。そこはやめましょう。
タイミングが合わないのか、それとも先生との組み合わせが悪かったのか、いずれにせよ、良い道場に巡り合うときは、不愉快な思いはまずしないはずです。
私の個人的な見解ですが、現代に生きる私たちは「最強」の武術を身に着ける必要はありません。
必要なことは「なるほど、こういう体の動かし方があるのか!」という気付きや「いつの間にか自分は体を守れるようになっているみたいだ!」という喜びです。
「礼節を重んじる」ことと「先輩が横柄である」ということは別です。
まずは門をたたいてみて、そして「楽しそうだったら始める」という気楽な気持ちが大切ではないでしょうか。
親御さんが判断しなければならない場合は、親御さんご自身が「この道場は合うな」と感じるかどうかの感覚を大切にしてください。
いまいち、感覚がわからないというときには、次の2点を意識してみてください。
①道場が清潔なこと
私の知っている良い道場はとても清潔です。
床の清掃は稽古ごとに行いますし、一日の終わりにはアルコール消毒するところも稀ではありません。
これはふたつの意味で重要なことなのです。
・万一怪我などがあった時に感染症がおこるリスクを考えているかということ
・指導者の方が道場を大切に思っているかということ<
これらが道場の清潔さに反映しているのです。
②指導者が親御さんに対して、魅力的、社会人として立派だと映ること
私の知っている良い指導者は、入門や見学に来る人に必ず丁寧に説明をします(受付の人が説明される場合もありますが、その場合もとても丁寧です)。
指導者に「お話を伺いたい」と言えば、対応をしてくれる場合がほとんどです。
その時に指導者をみて、魅力的だと感じられるか、社会人として尊敬できる人だと感じられるかどうかはとても大切なことなのです。
なぜこれが大切なのかというと、「道場」や「指導者」が「親御さん」にする対応は、「大切なお子さんを預かる」という意識があるかどうかを反映しているからであり、多かれ少なかれお子さんは「指導者」を通じて「大人」を学んでいくからです。
大きな道場であれば、受付で「指導される先生にお話を伺うことはできますか?」と聞いても良いでしょう。
いつも時間があるわけではないので、ちょっと待つことはあるかもしれませんが、たいていは先生に会わせてくださるはずです。
多くの道場では、入会するにあたって入会金と月謝の先払いを行います。
稽古着一式と入会金、月謝を合わせると、初期費用は3万円から4万円になることが多いはずです。
退会の時にも、数か月の指導料を払うことは稀ではありません。
そう考えれば、30分か1時間待ってでも、指導者を見ておくほうが良いでしょう。
「大事なこと」に挙げていないこと
最強の空手であるかどうか
さて、長々と書いてきましたのでもうお分かりかと思いますが、私は「最強の空手」が何かというのは、道場選びに全く必要のない議論だと考えています。
私たちは武士ではありませんし、また、戦国を生きているわけでもなく、21世紀を生きているのであり、会社員であり、主婦・主夫であり、また、学生です。
宮本武蔵の二天一流に対抗するにはどうしたらいいのか、ということは考えなくていいのです。
もっと言うと、「対抗しなければいけない状況に入らないよう努力する」か、「対抗する事態になったらとにかく逃げる」ということを体験するために、「空手」を習うべきだと考えています。
空手、合気、日本武道、軍隊格闘技、柔道……、
何でも構いませんが、格闘技を現代に生きる私たちが学ぶ意味は、
「こういう体の動かし方があるのか」
「自分はこういう風に体を動かす方が良いと思うな」
という気付きを得たり、
「いい汗をかいたなぁ」
という体験をしたり、親子ほど年齢が離れた人と同門として「今日も稽古に付き合ってくれてありがとうございました」とお互いに言えるような非日常を体験できることにあるのだと思います。
したがって、繰り返しになりますが「最強の空手」は教室選びにはほとんど関係ありません。
実践的であるかどうか
もっと深く考えてみると「実践的であるかどうか」も教室選びには関係ありません。
また、お子さんに習わせるのであれば、なおさら生兵法は大怪我の基ということを知っておく必要があります。
軍隊用語で「無力化する」という用語がありますが、対人においては「殺害する」という語とほぼ等しい意味です。
中国の思想家の孫氏は「兵に四路五道あり」と述べていますが、これは、軍隊には、
①進む
②引く
③左か右によける
④その場にいる
という5通りの選択肢がある、逆に言うとそれしかないということを述べたものです。
たとえば……
・夜のプラットホームで酔っ払いに絡まれたとき
・あるいは、お子さんがいじめに遭遇したとき
どう対応するのが理にかなっているでしょうか?
進んで打ちのめすべきでしょうか?
「空手」を通じて護身の心得を持っていても、万能ではありません。
相手は自分より強いかもしれません。
下手に手を出したら返り討ちになってしまうかもしれません。
仮に、相手を打ちのめしたとしても、それは犯罪です。
ではどうしたらよいのか?
それを学ぶのが「空手」を学ぶことだと考えてください。
「実践性」の議論は、ナイフで刺して来たらこう返す、寝技にはこう……等々、とにかく打ちのめす、という発想に偏りがちですが、相手が銃を持っていたならば逆らわないことが賢明です。
大切なことは、危機的な状態にあっても、冷静さを失わないことと、最低限自分の身を守れることです。
どうしても介入するのであれば、例えば、自分は相手を怒らせないようになだめつつ、周りのひとに助けを呼んでもらうという、という判断ができるようになることが大切だということです。
世の中を生きていく上での危機的な状況には、想定外のことばかりが起きるものです。
どれだけ空手が強くなったとしても、想定外の状況の時にどう対応するのか? 習得することなどはできません。
「空手」は「非日常」を疑似体験させてくれます。
相手が突きを放ってくる、相手が蹴りを放ってくる……、日常生活ではなかなか起こり得ないことです。
空手の稽古は、その「非日常」の中で、冷静さを失わず、落ち着いて対処できるようになることがその本質だと思います。
相手を倒すことは目的ではないのじゃ。
トラブルに遭遇しないように努力する。
仮にトラブルに巻き込まれたときでも、相手の気持ちも推し量れる冷静さを保ち、できる限り穏便にその場を収められるよう柔軟な気持ちを養う。
それが、「礼」を意識した、「空手」の「稽古」のあり方なのじゃ。
どの流派なのか
「教室選び」にあたって、「流派は何でも良い」ということが私の見解です。
再三述べていますが、空手という言葉自体が100年もたっていない用語ですし、空手の流派という概念が生まれたのはもっと最近です。
「空手」は、突きや蹴りといった、きわめて原始的な、日常生活で起こり得る危機的な状況を(非日常を)体験させてくれるものです。
その体験を通じて、強い身体と柔軟なこころを養うことを目的に、道場を選んでみると良いでしょう。
まとめ
「空手」は習い事なので、続けやすいことが大切です。
楽しく、かつ、トラブルに冷静に対応できるように、「非日常」を体験できる……
それが「空手」を習う意味なのだと考えています。
最後に、親御さんに大切にしてもらいたいことを述べて締めくくりたいと思います。
それは、教室や道場にすべてを任せないでお子さんの気持ちを尊重してほしいということです。
高校生や大学生になれば自分の判断で自分に合う場所を選ぶこともできますし、親御さんに強制されたからと言って不快な思いをしてまで道場に通うことはないでしょう。
しかし、小さいお子さんに習い事をさせているとき、小さいお子さんが練習を嫌がった場合に「あきっぽいのではないか」「これはこの子は周りに合わせられないので、続けることが修練になるのではないか」という思いを抱かれる場合が多いのではないでしょうか。
そういうときに、お子さんが感じていることを大切にしてほしいのです。
不思議なことに、日本では「耐えることが良いことだ」という風潮があるようですが、これはとても危険な兆候だと私は感じています。
やりたくないという気持ちを無視して道場に通っても、決して上達しませんし、良いことはありません。
私の知っているご自身が要人警護もされていた空手家さんは、お子さんに格闘技を習うことを勧めたものの、お子さんが「痛いのはいやだ」と嫌がったのでやめた、と仰っていました。
素晴らしい判断だと思います。
ご自身も空手の高段者ですので、良いところも悪いところもよく知っている空手家さんです。
縁があれば、遅かれ早かれ、お子さんが自分で「やりたい」というときは来る、だから、無理に始める必要はないと考えたのでしょう。
長文にお付き合いいただきありがとうございました。
皆さまが、良い道場に巡り合えて、有意義な「空手」の稽古を体験できることを祈念しております。