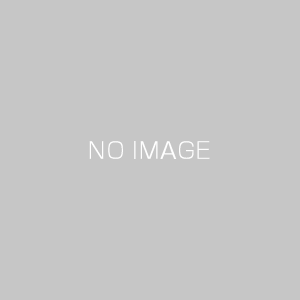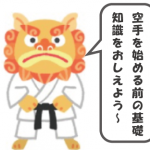格闘技や武道は人気のスポーツのひとつですね。
空手道も2020年の東京オリンピックの正式種目に加わったことで大きな注目を集めており、テレビ番組やCMで空手をしている選手を起用しているのをよくみかけるようになりました。
私の父も、空手の道場を持っており有段者で指導をしており、私も有段者で指導員をしております。
オリンピックの種目に決まったことで、見学や体験に来られる小中学生や親御さん、社会人が増えています。
空手に対して「空手は戦って痛いもの」「ケンカが強くなるもの」「流派の違いは戦わない型をするか相手と戦う組手の違いでしょ…?」などのイメージをお持ちの人もいらっしゃいますが、実際にはどれも違うのです。
今回は、
「これから空手を習いたい」「習わせたいと思っているけれど、流派がたくさんあってどこの道場に入門すればわからない」
という人や、
「すでにどこかの流派に所属しているけれど、うちの流派はオリンピックの選考の中に入っているのか分からない」
といった人に、
それぞれの流派の違いや歴史、オリンピックの選考基準は流派に影響するのかを詳しく解説していきます!
ぜひ近くの道場を見学に行く際の参考にしてみてください!
目次
空手とは
まず、皆さんは空手についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
剣道や柔道と同じように武道のひとつですが、空手に関しては「相手と戦うもの!」というイメージを持っている人が大多数。
空手は、武器を待たず拳や足技を使い、全身を使って相手の攻撃から身を守りながら攻撃または反撃することを目的とした武道であり、格闘技です。
沖縄で発祥し、その後それぞれの特徴ごとに派生したことで、現在では様々な流派に分かれています。
知っておいて!!空手は心を鍛える場所!
ここで皆さんに知っておいてほしいのは、
空手道は、相手が何もしていないのに自分から手を出したりしてはいけないことです。
空手だけではなく、柔道や剣道、弓道などの武道でもそうですが、
武道とは言葉の通り「武士の道」であり、お侍さんが、自分自身の心や技を鍛錬するための日々の稽古として始まったものです。
道場に見学に来られる親御さんの中にも
「子どもがいじめられっ子なのでケンカを強くさせたい」とおっしゃる人がいますが、
「ケンカが強くなって相手を負かすのではなくてまずは、いじめられっ子に負けない強い心になるように練習をしていこうね」と話をします。
いくらパンチやキックが強くなっても、思いやりや感謝の心を鍛えなければ、今度は相手を傷つけてしまいます。
これから空手を習わせたいと考えている人は、どうかケンカの強さではなく、子どもの心を強くさせるために空手を習わせたい、と思ってもらいたいというのが私の切なる願いです。
一緒に体だけではなく心も鍛えていきましょうね!
空手の歴史
さて、先ほど空手にも流派があるとお話ししましたが、なぜ空手にはたくさんの流派があるのでしょうか?
ここからは、わたしが簡単に空手の歴史について話をしよう。
空手の歴史は古く、1700年代~1800年代の琉球王国時代、現在の沖縄県で始まったと言われておる。
その中でも首里手、那覇手に分けられ、貿易関係にあった中国から伝わった拳法と合わさり「唐手術」という護身術であった手を、琉球王国の士族であった首里手の糸洲安恒(いとすあんこう)師や那覇手の東恩納寛量(ひがおんなかんりょう)師などによって、1900年代に本土で小学校の体育授業として取り入れられたことで「空手」として普及していったのじゃ。
また、現在の型演武で最も普及している平安(ピンアン)も、糸洲師によって危険のないように改変を加えられ、現在のような形になったのである。
糸洲師から教えを受けた弟子たちによってそれぞれ流派が派生し、現在では、四大流派と言われる松濤館流・和道流・糸東流・剛柔流やフルコンタクト、その他派生した多数の流派によって、現在では日本だけではなく世界各国に広がっているのじゃ。
沖縄県から始まった空手は、今では名前もよく知られ、マンガやテレビ、CMだけではなく国際試合やオリンピック種目となり、そのため競技人口はまだまだ増えると言われおる。
空手の流派
さて、少し空手の歴史や空手の心得をご紹介したところで、
次は空手の流派について説明していきます。
空手の流派はとても多く、先ほど紹介した四大流派や、フルコンタクト以外にも多くの流派が存在します。
流派の大きな違いは、基本と言われる型に繋がる立ち振る舞い、演武である型、型や組手の試合のルールです。
ご自宅の近くの公民館や小学校などの施設などで道場を開いている空手も、これからご紹介する流派に当てはまります。
しかし、ポスターだけではどこの流派なのか、そもそもの流派の違いについていまいち理解出来ず、「初心者だからどれを選んでも一緒ではないの?」と思ってしまうこともあるでしょう。
少しずつですがそれぞれの流派の特徴は違っていて、各流派それぞれ先代宗家の教えを引き継ぎ、切磋琢磨し技の改良や進化を続けています。
ただ、四大流派の組手に関しては、全空連でのルール統一のため、構えや間合いの摂り方に若干の差があるものの特別な差は見受けられないため、ここでは割愛しますね。
では、今回は数ある流派の中から、四大流派・フルコンタクトの特徴をご紹介します。
四大流派
まずは、現在の空手道の普及のきっかけとなった四大流派である松濤館流・和道流・糸東流・剛柔流についてお伝えします。
それぞれの流派も、これからさらに派生して様々な流派に分かれていますが、数がとても膨大であるため、親元の流派の特徴をご紹介します。
松濤館流
開祖は船越義珍(ふなこしぎちん)師で、没後のちに受け継いだ弟子たちによって雅号である「松濤」をもとに松濤館流と名乗られるようになりました。
松濤館は遠い間合いからの攻撃を特徴とし、動作がダイナミックでもあります。
テコンドーの元になったとも言われ、空手の流派の中でも所属している人数が多い流派です。
和道流
開祖は大塚博紀(おおつかひろのり)師で、松濤館流の船越師が師匠にあたります。
船越師の教えをもとに、柔道や剣術などの要素を加えた和道流が誕生しました。
唯一、本土での発祥した流派であり昭和に誕生した比較的新しい流派です。
柔術や剣術の要素が加わっていることで、柔道に似た投げ技や足技などの技も多いことが特徴です。
糸東流
開祖は摩文仁賢和(まぶにけんわ)師で、那覇手と首里手の糸洲師と東恩納師の頭文字を取り「糸東流」と名乗ったことが始まりです。
それぞれの教えや古武術などを改良し、現在の形になったと言われています。
現在では世界各国に広がっている流派でもあり、糸東流をもとに複数の会派も創設されている流派です。
技は細かく派手ではありませんが、実践に一番強く意識していることが特徴です。
剛柔流
開祖は宮城長順(みやぎちょうじゅん)師で1930年ごろ当時、唐手であった系統を「剛柔流」と名乗ったことが始まりであり、那覇手の東恩納師から学んだ教えをもとに作られたと言われています。
剛柔流は近距離での受けや払いを特徴とし、また、攻撃よりも自身を守ることに重点を置いていることも特徴であり、「ムチミ」は剛柔流独自の接近戦での戦い方となっています。
フルコンタクト
フルコンタクトは、組手の際に寸止めの手法を取らず直接打撃をする形式を採用している団体です。
フルコンタクトは四大流派とは違い流派ではなく団体名で、有名な団体に極真会館がありその他のフルコンタクトを採用している団体もこの極真会館から派生した団体です。
世界各国に会派があり、流派の垣根を超えて強さを追及する人の集まりでできています。
現在では、極真会館の開祖である大山師の教えを受けた弟子たちによってさまざまな団体が派生しています。
フルコンタクト系は直接相手のボディに突きや蹴りを当てるため、総合格闘技としても参加することもあり、メディアやテレビなどで極真空手の名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
フルコンタクトの中でも昭和に空手ブームの火付け役となり、極真空手の礎を築かれたのが現在の極真会館の開祖である大山倍達(おおやまますたつ)師です。
前身である大山道場でマンガ「空手バカ一代」のモデルにもなった人物で、当時、4大流派の寸止めでの組手が主流でしたが直接打撃であるフルコンタクトを提唱し新たな団体のために邁進した人物です。
のちにできる系統の団体は、いずれも大山師の弟子たちが新たに立ち上げた団体で、後にも先にも極真会館はフルコンタクトの中では最も道場生が多く、現在でも空手道の新たな時代を切り開いています。
以下に、フルコンタクトの道を開いた極真会館を含めた会派の特徴をご紹介します。
こちらも会派が多くあるため、4大流派同様に有名な団体について綴っていきます。
極真会館
開祖は先ほど紹介した大山倍達師であり、現在は松井章圭(まついしょうけい)さんが館長を務められています。
極真会館は国際空手道連盟も運営しており、社会貢献を目的としているフルコンタクトの中では大きな団体です。
組手の試合方式は直接打撃ですが、基本や型も大事にしており、全国各地、海外支部があることで地方大会や全国大会が行われるなど大きな団体です。
四大流派同様に昇級・昇段審査があり帯の色も変化していくため、組手での直接打撃や型の方式はやや違いますが、基本からしっかりと学べる体制が整っています。
メディアへの出演も多く、極真カラテ=極真会館のイメージも強いかと思います。
極真館
極真会館の道場生で松井派であった盧山初雄(ろうやまはつお)さんによって創設された団体です。
極真会館から分裂した団体の中で唯一、突きや手技による顔面攻撃を認めた組手の試合を行っています。
空手の技だけでなく、護身術や太極拳や中国武術的要素のある型も取り入れているのが特徴のひとつです。
フルコンタクトの中では、顔面攻撃ゆえの間合いを取らない接近戦での試合形式となっています。
新極真会
極真会館の道場生であった緑健二(みどりけんじ)さんによって創設されたNPO法人の団体です。
現在の極真会館の館長である松井章圭さんとの確執によって新たな団体ができた、という経緯があります。
会歌があり、長渕剛さんが作詞作曲したことでも話題になりました。
試合のルールは極真会館の試合方式を採用しており、極真会館と大きな差異はありません。
メディアの露出も多く、試合中継やレギュラー番組を持っていることからフルコンタクト空手の普及にも力を入れている団体です。
芦原空手
極真会館の道場生であった芦原英幸(あしはらひでゆき)さんによって創設された団体です。
マンガの「空手バカ一代」のモデルとしても登場しており、愛媛県で極真会館の支部長を務めたのちに、大山師との確執によって除名を受けたのち創設されました。
芦原空手は少林寺拳法や合気道などの武術を織り交ぜた「サバキ」と呼ばれる、攻撃される前に相手に有利なポジションを取って攻撃することで相手に攻撃をさせない独特な立ち回りがあります。
フルコンタクト空手のイメージからすると直接打撃の打合いのイメージがありますが、芦原空手は護身術に近い印象を受けます。
芦原会館主催の試合は行っていないため、フルコンタクト全般での際に出場する形になります。
正道会館
極真会館の道場生であった石井和義(いしいかずよし)さんによって創設された団体です。
極真会館の芦原道場時代に大阪で支部長を務めますが、現在の芦原空手の創設者の芦原英幸氏との確執によって自らも団体を離れ新たに作られた団体です。
組手の中に掴みの動作があり、K-1参加や格闘技オリンピックなどへも参加し、空手の垣根を超えてより実践的なプレーが多いのが特徴です。
テレビやCMによく出演され、K-1などでのレフリーなども務めておられる格闘家の角田信朗さんも正道会館の出身です。
大道塾
大道塾は極真会館出身の東考(あずまたかし)さんによって創設された団体です。
空手の禁止項目であった手による顔面打撃や投げ技・絞め技を認めた格闘空手で空道と名乗っています。
柔道の要素も取り入れており、空手の要素は比較的薄く、フルコンタクトを超えた独自のルールを採用しています。
稽古自体は空手の要素を取り入れ基本や移動、組手といった一連の流れであることが多いのですが、構えや組手での動作はボクシングや他の格闘技に近いものがあり、組手の試合時には頭に防具を着用します。
誠道塾
誠道塾はアメリカのマンハッタンに本部がある団体で、極真会館出身の中村忠(なかむらただし)さんによって創設された団体です。
もともとは極真会館の支部をニューヨークに作りましたが、極真会館の意見の相違により独立し誠道塾を創設されました。
現在の昇級審査の際の色帯式は中村氏の発案だと言われ、現在は他流派もこの方式を取り入れています。
大山師の後継者になると言われていたこともあり、極真会館の要素を取り入れた防具を使用した試合形式を採用しています。
空手を習いたいけどどの流派を選べばいいのかわからない時
「流派の特徴や歴史について何となくわかったけど、初心者だからどの流派を選べばよいのか分からない」という場合、どのように選択すればよいのでしょうか?
私の道場生の中にも、実際に他の流派から再度入門してきた子どもや部活動では他の流派のため兼任している生徒もいます。
道場選びで大切なことをまとめましたので、ご紹介します!
流派の選び方
流派を選ぶ際、ご家族の中に空手の経験者がいらっしゃるのであれば入門に関わらず話を聞くのが一番ですが、ご家族に空手の経験者がいらっしゃらない場合は、まずは、四大流派のように寸止め形式での組手なのか、フルコンタクトのように直接打撃のある組手なのかどちらを選択するかによって今後の試合形式が変わってきます。
また、組手のように戦わず、演武である型を選択するのであれば、四大流派とフルコンタクトどちらでも好きなほうを選択するとよいでしょう。
組手を極めていきたい場合
空手のイメージと言えばやはり、1対1の組手と呼ばれる戦いのイメージが強いかと思います。
四大流派は日本空手道連盟(通称:全空連)によってルールが統一され、直接打撃を禁止する「寸止め」での試合であり、万が一体に触れる行為があっても引手をとるため打撃による大きなけがに繋がりにくく安全です。
一方フルコンタクトは直接打撃による試合形式になりますので、ケガや骨折の可能性は四大流派に比べて危険度は高くなります。
しかし、強さを求める場合や、今後他の格闘技と複合して総合格闘技として戦うことを希望するのであればフルコンタクトを選択し、道場が行っている試合に出場することでフルコンタクト制を採用している団体で活躍することができます。
型を極めていきたい場合
演武の正確性や気迫、基本に忠実であるかなどの技を競う型を習得したい場合には、四大流派のいずれかに入門するべきという意見を聞いたことがありますが、実際にはどうなのでしょうか?
確かにフルコンタクトは組手のイメージが強いですが、極真会館や新極真会の試合でも型の試合を行っています。
伝統空手である四大流派は、基本動作や相手からの攻撃をかわすための身のこなしや、気迫で相手を追い詰めるといった動作を型として行い、とても迫力があります。
各流派によって若干の違いがあるものの、大きな試合に出場する際には全空連が指定する型の中から演武する型を選択するため、どの流派も共通しており各流派の特徴は出にくくなっています。
また、筆者は四大流派に所属していますが、フルコンタクトの極真会館の型を試合で拝見したことがあります。
開祖である大山師は松濤館流と剛柔流を習っていたこともあり、四大流派に見劣りせずとても迫力のある型で四大流派の型と大差ないかと思います。
よって、選択するのであれば、組手をする際に寸止めなのかフルコンタクトなのかどちらを選ぶかにあるでしょう。
型や組手についてよくわからない場合
「いろいろ書いてあるけど方も組手もやったことないからよくわからない……」それでも、「空手には興味がある!!」という場合は、近くの道場に一度見学に行くことをオススメします。
私の道場でも見学や実際に空手の体験する機会を設けていますが、まずは実際にご自分の目で確認してみるのが一番ですよ。
また、道場を開いている先生や指導員の流派やその道場での考え方、試合成績などを教えてくれるため、それが参考のひとつにもなります。
何もわからないからこそ、ご自身や子どもにあった道場をみつけることができると思いますので、近くの道場に足を運んでみるといいかもしれません。
また、現在では、HPをもつ道場や各流派のHPに加入団体名や支部名、連絡先などを記載していることが多いので、各HPからアポイントを取ることもオススメです。
流派によってオリンピックに出場できないことってあるの?
オリンピックの正式種目となったことで、子どもに空手を習わせたいという親御さんが増えています。
見学に来られる親御さんの質問で多いのも「ここの流派はオリンピックに出られる流派ですか?」という質問です。
せっかく習わせるのであればオリンピックを目指してほしいと思うのもまた親心で、気になるところではないでしょうか?
オリンピックと流派の今後についてご紹介します!
四大流派とオリンピック
オリンピックの種目に決定しましたが、オリンピックでのルールは世界空手道連盟の規則に乗っ取り型や組手の試合が行われることが決まっています。
四大流派は全空連で組織されており、もちろん世界空手道連盟に加入しているため、四大流派のいずれかに入門していて選考基準になる各試合で好成績を収めれば、オリンピックに出場することは可能になります。
これから空手を始める場合であってもオリンピックの正式種目であるうちは稽古を続け、努力を続けることでオリンピックの出場も夢ではないかもしれません!
フルコンタクトとオリンピック
今回のオリンピック種目に選ばれた空手の種目のうちの組手は「寸止め」のルールを使用した試合形式になっています。
これは四大流派が加盟する全空連および世界空手道連盟のルールに基づいて決定されました。
ですから現在のところ、直接打撃の試合形式であるフルコンタクトのオリンピック出場は難しいと言われています。
フルコンタクトの立役者である大山師もご存命のころIOC(オリンピック委員会)にフルコンタクト制の採用を認めてほしいと活動を続けておられましたが、安全を保障することができないとして採用には至りませんでした。
しかし近年、フルコンタクトも複数の団体が全日本フルコンタクト連盟を結成し、フルコンタクトのオリンピック出場に向けての活動が活発になっています。
また、極真会館などのフルコンタクトの連盟でも、4大流派の全空連に賛同し、世界空手道連盟のルールでオリンピックに参加したい旨を伝えています。
大山師がお亡くなりになられたことで内部分裂を起こし、大山師の元で稽古を積んでいた道場生それぞれの確執や思想によって極真会館をもとにおおくの会派が誕生しました。
それぞれが独立しフルコンタクト空手のジャンルを広めてきましたが、現在ではそれぞれの団体が和解や合同の試合を行うなどして、友好な関係を築いているように思います。
現時点でのオリンピック参加は厳しいですが、これから先、ルールの改正や安全面が確保されれば、オリンピックの空手競技である組手種目の中にフルコンタクトの部門ができるかもしれません。
フルコンタクトは、今後のオリンピック出場に向けた動きに関してまだまだ進展がありそうです!
まとめ
今回は、空手道と流派について歴史や特徴、オリンピック出場などを含めてご紹介しました。
空手は沖縄から始まり、これまでにたくさんの宗家や館長によって守られ伝えられてきた武道です。
現在注目されている空手は今後ますます競技人口が増えていきますが、まずは技や力よりも心の鍛錬が一番であることを知ってほしいと思っています。
私も指導者として、これから空手を始める皆さんのお役に立てるよう様々な情報を発信できればいいなと思っております。