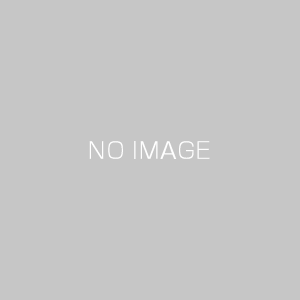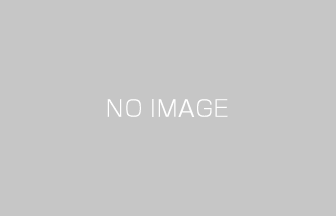幼少期から空手をはじめ早15年。今では組手専門で日々稽古に励んでいる筆者が記事をお届けします。
「空手のなかでも【フルコンタクト空手】ってどんなものなの? よく聞くけど、詳しくは分からない」
と思っている空手好きあるいは空手初心者も多いはずです。
フルコンタクト空手とはずばり「相手に当ててOK」なルールの元で行われる組手のこと。
そこで今回は、フルコンタクト空手の歴史や流派、ルール、稽古方法まで詳しく解説していきます。
後半にはフルコンタクト空手の【試合動画】もご紹介しているので、ぜひ最後までお楽しみください。
そもそもフルコンタクト空手って?
「フルコンタクト空手」。
空手好きもしくは空手初心者なら一度は耳にしたことがあるはず。
フルコンタクトとはずばり「直接打撃制」を意味しています。

文字通り、「相手に当ててもOK」ということ。
フルコンタクトの試合を初めて見ると、まるで殴り合いの喧嘩をしているような印象を受けます。
当然ながら「なんだか痛そう…」「激しすぎて自分にはできなさそう…」とも思ってしまいます。
また、フルコンタクト空手は従来の伝統空手の「寸止め」に異を唱えたものでもあるんです。
だからこそ試合風景も、【相手に当ててはいけない伝統空手】の組手とはまったく異なります。
フルコンタクトの歴史は?いつから始まったの?
そもそもの「空手」(当時は唐手)の歴史は、戦前の琉球時代までさかのぼります。
沖縄を中心に栄えた空手ですが、当時はまだフルコンタクトは存在しておらず、「寸止めルール」が一般的でした。
しかし戦後になり、1969年に空手家「大山倍達(おおやま ますたつ)」寸止めルールへの異論を唱えました。
これがフルコンタクト空手の起源となります。
同時に「極真空手」が誕生し、以降、【フルコンタクトを主とする極真空手ブーム】が到来し、現在に至ります。
極真空手の流派は?
フルコンタクト空手は主に極真空手で行われています。
ただ、ひとくちに「極真空手」といっても、いくつもの流派に別れており、各流派ごとに特色があります。
また、先述したように、大山倍達の意思を受け継いだ「極真会館」がルーツとなており、そこから次々と新たな流派が誕生しました。
極真会館
今もなおもっとも会員数が多い「極真会館」。北は北海道、南は沖縄まで、全国各地に道場を構えています。大山倍達氏の意思を受け継ぎ、現在では松井章奎氏が代表を努めています。
新極真会
極真会館から派生して生まれた「新極真会」。
【全世界空手道連盟】として活動しており、日本国内のみならず海外にも支部を持ち国際交流も積極的に行なっている流派です。
さらに「社会貢献」にも注力している流派で、チャリティー活動も精力的に行なっています。
極真館
大山氏の意思を引き継ぎ2003年に創設された「極真館」。
型や組手はもちろんのこと、サイ・棒・ヌンチャク・トンファーといった武器術も体得できます。
また組手においては直接打撃制が取り入れられているものの、「無防備に相手に接近することへの制約」や「ガッツポーズの禁止」などがルールとして定められています。
極真会館松島派
こちらも大山氏の意思を受け継ぎ、極真会館から派生した流派。
道場名の通り、松島良一氏が代表を努めており、世界のいたるところに支部を持ちます。
また「MATSUSHIMA極真空手ワールドカップ」という国際大会も開催されています。
フルコンタクト空手は「極真以外」でも行われている
「フルコンタクト空手といえば極真」をイメージするのですが、必ずしも極真空手だけで行われている訳ではありません。
伝統でも極真でもない「独自の道場」や、「国際組織」など、フルコンタクト空手は至るところで広まっているのです。
なかでも有名なものをご紹介しましょう。
WKO(世界組手連盟)
2007年に作られたフルコンタクト空手の国際組織です。
タイに拠点を構えており、日本をはじめロシアやアメリカなど、世界20カ国もの団体や道場が加盟しています。日本では「白蓮会館」が代表例です。
白蓮会館
1984年に創設された「憲法の流派」です。
空手というよりも少林寺拳法の色が強く、突きや蹴りをはじめ、投げや関節技を使った技が特徴的。
士道感(世界空手道連盟)
顔面攻撃や組み技も取り入れている空手団体「士道感」。
数ある流派のフルコンタクト空手でも、制約が少ないのが特徴です。
海外にも多くの支部を抱え、ルール上寝技や絞め技もOKとなっています。
JFKO(全日本フルコンタクト空手道連盟)
国内でフルコンタクト空手を取り入れている数多くの団体が所属する組織「JFKO」。
2003年からは、流派の垣根を超えた「フルコンタクト空手道選手権」も開催しています。
フルコンタクト空手大会の仕組みは?
フルコンタクト空手の大会、試合がどのように行われるのか具体的に解説していきます。
数多くの流派に分かれている分、大会の仕組みやルールも複雑になっています。
大会は各流派ごとに開催される
多くの場合、大会は各流派ごとに開催されます。
たとえば「極真会館なら極真会館内の大会」、「極真会館松島派なら松島派の大会」となります。
もちろん流派の垣根を超えてフルコンタクト空手の大会が行われることもありますが、その場合は先述した「JFKO」や「WKO」が主催していることがほとんどです。
試合でのルールは?
試合時間は2分
試合は「2分間の流し(もしくは3分)」で行われます。
基本的には、主審による「ストップ」コールが発せられるまで時間が止まることはありません。
かなりあっという間です。
見てわかる通り、3分12ラウンドのボクシングや、4分の柔道と比べても圧倒的に短くなっています。
勝敗の決め方は?
伝統空手では、技のキレや【決まり具合】を重要視した「ポイント制」が導入されていますが、フルコンタクト空手は少し異なります。
試合に勝つためには「一本勝ち」をする必要があり、主に突きや蹴り、さらには肘打ちといった技を出し合います。
審判は一本をどのように判定しているの?
判定が一本となる条件はいくつかあり、具体的には「相手が3秒以上ダウン」「相手の戦意喪失」、「2回の技ありによる併せ一本」です。
これらは全て主審の判断に委ねられます。
勝敗が決まらない場合は副審を含む判定に
勝敗が決まらなかった場合は、主審1名と副審4名による判定となります。
「技の精度」や「気迫」などを加味した上で判定し、5名中3名以上の指示で勝利となります。
伝統空手ではNGな行為もあり
寸止めが基本とされている伝統空手には禁止行為がたくさんあります。
フルコンタクト空手では、伝統空手では絶対にありえない「下半身への蹴り(ローキック)」や、「グランド状態での攻撃」なども認められています。その他にも様々な攻撃が認められています。
もちろん禁止行為もある
伝統空手と比べて攻撃の幅が広いフルコンタクト空手ですが、もちろん禁止(反則)行為もあります。
なかでも「金的への攻撃」「頭突き」「顔面への突きや肘打ち」などが代表例です。
あからさまに相手を傷つけるような行為は禁止です。
防具はつけるの?
フルコンタクト空手では、伝統空手のような目立った防具を付けることはありません。
ただ、まったく付けないという訳ではなく、「体を守るために最低限必要な防具」はつける場合が多いです。
たとえば金的を守る「ファールカップ」や、歯を守る「マウスピース」、拳を守る「オープンフィンガーグローブ」などが代表例です。
流派ごとにルールが異なるので、あらかじめ理解しておく
流派や組織によってルールが少し異なります。
なかには顔面攻撃が認められていたり、関節技があったりと、流派によってばらつきが見られます。
・極真会館(松島派):顔面寸止め有効、下段回し蹴り・膝蹴りやカカト落とし禁止
・新極真会:2回連続での押しは反則、有効な捌きはOK
・極真館:ウエイト制での顔面攻撃あり(拳グローブと肘サポーターの着用義務)
・白蓮会館:投げ、関節技あり
・JFKO(全日本フルコンタクト空手道連盟):掴み、掛け、押し、抱え込みは反則
階級や大会によってルールも変わる
ウエイト制を導入している大会が多く、階級によってルールが変わることもあります。
「ウエイト制でのみ認められるルール」や「無差別階級でのみ認められるルール」などバラつきがあるのが事実です。
また、大会によってもルールは変わってきます。試合前には「ルール規約」をきちんと読んでおく必要がありますね。
激しくぶつかりハード!しかし心身ともに強くなれる
フルコンタクト空手の組手は、正直かなり痛いです。
見ているだけでも伝わってきますが、実際に自分が試合に出ると、かなりハードに感じることでしょう。
しかし言い方を変えれば、これこそがフルコンタクト空手の魅力でもあります。
ときにアザができたり、体を痛めてしまうこともあるかもしれません。
ただ、相手と激しくぶつかり合うことで心身ともに強くなっていくのです。
どうやって稽古を進めていけばいいの?
当然ながら、フルコンタクトの試合に臨むうえで、十分な稽古は必要不可欠です。
強くなるため、あるいは自分の身を守るためにはどのような練習が必要なのか見ていきましょう!
基本的な稽古方法は?
ケガ防止のための「準備運動」を入念に行う
フルコンタクト空手は相手と激しくぶつかり合うので、当然ながらケガのリスクも高まります。
ケガをしてからでは遅いので、あらかじめ「準備体操」や「柔軟運動」を行なって体を慣らしていきましょう。
特に股関節や指の関節をほぐしておくのが◯。
体の柔軟性が上がれば、ケガ防止はもちろんパフォーマンス向上にもつながります。
スタミナをつける
試合時間は2分間と短いですが、動き続ける上に、相手の攻撃に備えて精神を研ぎ澄ますので、かなりの体力を使います。
2分間を戦い抜くためにも、走ったり、試合形式の練習をたくさん行うなどをして、スタミナをつけておくとよいでしょう。
インナーマッスルを鍛える
突きや蹴りを安定させるためには、体の軸をしっかりと作る必要があります。
そこでカギになるのが「インナーマッスル(体幹)」です。
腹筋や腰周り、それから脊柱起立筋などを鍛えるトレーニングを行うと、体の軸が安定しますよ。
ミット打ちを行う
技を磨けるのは必ずしも実践練習だけではありません。
まだ試合に慣れていない人や、ひとつひとつの技を磨きたい人は「ミット打ち」がおすすめ。
大きなミットを使って、突きや蹴りのキレ・精度を高めましょう。フルパワーで技を出せる上に、「間合い」を確かめることもできます。
試合で結果を出すために必要な練習は?
ひたすら実践を積む(スパーリング)
ある程度慣れてきたら、相手をつけて実践をしましょう。
どんなスポーツでもそうですが、「試合に慣れるためには試合をやる」がベストです。
うまく時間を作って、道場で試合形式の稽古をしましょう。
実際に試合やスパーリングを行うことで、相手との距離感や自分の間合い、試合の雰囲気を肌で感じることができます。
ケガしない程度に、徐々に組手のコツを掴んでいきましょう。
自主練を積極的に行うこと
メニューは基本的に、ミット打ち、スパーリング、実際の試合、のいずれかに限られます。
「必ず試合に勝てるスペシャルメニュー」は存在しないので、淡々と自主練種を行うことが大切です。
量をこなして場数を踏みましょう!
強い相手と稽古をする
当たり前ですが、「強い人はいつも強い人と練習している」んです。
自分より格下の相手とばかり練習していても、試合で勝つことはできません。
ある程度実力がついてきたら、格上の相手を練習しましょう!
最初は怖いかもしれませんが、「周りが強い環境」に身を置くことで、自分の実力も引き上がります。
試合の動画はこちら
【国際フルコンタクト空手道選手権大会・男子重量級準々決勝】
【第1回国際フルコンタクト空手道選手権大会・女子中量級】
【全日本空手道選手権大会(新極真会)】
伝統空手にはない「強さ」が磨かれる
フルコンタクト空手について詳しく解説しました。
「フルコンタクト空手=極真」なイメージがありますが実はそうでなかったり、流派や大会によってルールが変わったりと、かなり複雑になっています。
また、相手と激しくぶつかり合うことから、伝統空手よりもハードな側面があると思います。
ただ裏を返せば、フルコンタクト空手だからこそ成長できる部分もあるんです。
ハードな練習や試合をやり抜くことによって、強い精神力や体力を手に入れることができるのは大きな魅力ですよね。
当然ながら「礼儀」も磨かれるので、人間としても大きく成長できることは間違いありません。
フルコンタクト空手を深く知った上で稽古に臨めば、さらに練習のモチベーションも上がるはずです。
きっと、一皮も二皮も剥けた、たくましい人間になれることでしょう。