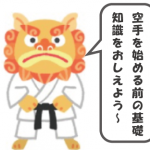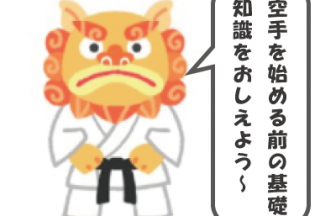皆さんは「空手」にどのようなイメージを持っているでしょうか。
最近は、テレビやYouTubeで「型」が多く紹介されていますので、型の美しさについてのイメージを多く持たれている人もいらっしゃるかと思います。
ご年配のかたは、梶原一騎(「巨人の星」の原作者と同一人物です)原作の「空手バカ一代」の極真空手のような、激しい実践的な武道を連想されるかもしれません。
空手が東京オリンピックの正式種目となったため、急激に空手に興味を持つ人が増えています。
しかし、インターネットをちょっと調べるだけで、「武道空手」「競技空手」「フルコンタクト空手」など、聞きなれない言葉が現れます。
これは、「空手」には非常に多くの「流派」があり、それぞれの「流派」ごとにルールが異なっているためです。
このページでは、オリンピックでいう「空手」が正統と認める、四大流派についてご説明します。
対比して、いわゆるフルコンタクト空手である、極真空手についてもご説明します。
この記事を読んでいただければ、だいたいの流派がわかるようになり、オリンピックの楽しみも増えるようになりますよ。
また、これからお子さんに空手教室に通わせようかと迷っている人には、どんな道場に通うべきかこの記事を参考にしていただければ幸いです。
目次
そもそも空手って何?
情報量が多すぎる! あえて分けるなら「寸止め」か「フルコンタクト」
先ほども述べましたが、「空手」についてインターネットをちょっと調べるだけで、「武道空手」「競技空手」「フルコンタクト空手」など、聞きなれない言葉が現れます。
これは「空手」には非常に多くの「流派」があり、それぞれの「流派」ごとに稽古方法、昇段の仕組み、目指すものが違うからなのです。
分類は難しいのですが、あえて分けるとすると、
「競技ルール」として、「寸止めルール」を採用しているか、「フルコンタクト」を採用しているか?
という基準がわかりやすいでしょう。
「寸止めルール」とは、相手をノックアウトするような強打を認めず、ポイント制で勝敗を決定するルールのこと。
オリンピック空手は、基本的には「寸止めルール」を採用しています。
これに対して、「フルコンタクト」とは、防具を付ける場合と付けない場合、顔面への攻撃を認める場合、認めない場合などがありますが、相手をダウンさせる強打を「一本」として勝敗を決するルールです。
主要な団体に極真会館があります。
こちらは、キックボクシングや、総合格闘技などへ大きな影響を与えて今日に至っています。
- オリンピック空手の主催団体「全日本空手道連盟(全空連)」に古くから所属する「四大流派」は「寸止めルール」を採用しているケースが多い
- 「四大流派」から距離を置き実践性を追求した、「極真会館」などが「フルコンタクト」の代表格
ちょっと歴史に触れてみよう 古いようで新しい「空手」
ここで「空手」の歴史に少し触れてみましょう。
実は「空手道」という武道は、誕生してから百年経っていない名称なのです。
「空手」という枠組みがはっきりしていないのは、そのためだともいえるでしょう。
空手は日本の武道ですが、発祥の地は沖縄だといわれています。
中国の拳法の諸派が、江戸期頃、薩摩藩の支配下にあった琉球で独自の発展を遂げたものが起源とされています。
元々「てい」や「唐手」などと呼ばれ、一部には武器術も含まれている武術体系でした。
「空手道」が成立するのは、大正・昭和になってからです。
1922年(大正11年)、文部省が主催した体育展覧会、講道館で行われた演舞などを契機に徐々に、日本の武道として認知されるようになり、昭和になってようやく「空手」という表記が用いられるようになりました。
「四大流派」はこのころ成立しました。
成立からわずか百年で、「空手」は日本のみならず、海外にも爆発的に広がったのです。
そのため、ルールも競技としての理念も流派ごとに統一性を欠いており、いまなお、すべての空手を統一する団体はないといわれています。
全空連の7月1日の資料によると、日本での「空手」の愛好者は200万人、世界での「空手」の愛好者は1億3000万人とされています。
ただし、全空連と協力はしているものの、参加していない極真会館の会員数1200万人はここには含まれていません。
教室を選ぶにはどうしたらいいの? 基本に帰ろう!
では、空手教室を選ぶときに、どんなことに注意すればいいのでしょうか?
様々な習い事に共通だと思いますが、世界クラスの選手になりたいとか、将来をその道にかけたいというのでなければ、流派のことは難しく考える必要はありません。
ただ、オリンピックの空手と系統が近いのは、「全空連」に所属している流派の「寸止め空手」です。
「形」の美しさや、オリンピックの空手に関心があるのであれば、「フルコンタクト空手」(極真会館など)は避けたほうがよいでしょう。
逆に、「フルコンタクト空手」は、キックボクシングや、総合格闘技などに近いところがありますので、より「実践的」な護身術を望むのであれば「フルコンタクト空手」を選ぶべきです。
大切なことは下記の三点です。
- 指導者が信頼できるかどうか
- 道場が良い雰囲気をもっているかどうか
- 自宅から無理なく通える場所にあるかどうか
「空手」は女性でも子どもでも習得できる武道ですが、それでも危険管理は大切です。
道場の指導者を信頼できることが第一前提です。
そして次に、「空手」の稽古はどの流派であっても沢山の人々と一緒に稽古をするため、技だけではなく、「相手のことを思いやること」などを学んでいくのですが、これができている道場は自然と良い雰囲気になっています。
最後に、「空手」は体力を使います。
継続して稽古するためには、行き帰りが負担にならない立地であることは重要です。
また、お子さんに習わせる場合であれば、送り迎えについても考える必要があるため、遠方の教室を希望する際は慎重に検討しましょう
オリンピックに空手が入るって聞いたけど?
前述の通り、空手は元々は数百年の歴史を持つ由緒ある武術ですが、「空手」として体系化されてから百年経っていません。
日本国内では1959年に全日本空手道連盟(旧、全空連)が結成され、防具付き「フルコンタクト」の競技ルールが提唱されましたが、結局不採用となりました。
1969年に公益財団法人全日本空手道連盟(現、全空連)の設立後、「寸止め」ルールが採用されましたが、「フルコンタクト」ルールを採用している団体もあり、国内での統一ルールはないまま現在に至っています。
実は、オリンピック競技に「空手」を採用する提案をおこなったのは日本の空手団体からではなく、スペイン・マドリッドに本拠地を置く、世界空手連盟(World Karate Foundation)だったのです。
世界空手連盟は日本の「四大流派」を正当な流派として認め、全空連とは採用するルールが異なります。
「寸止めルール」を採用しています。
オリンピックを楽しむ観点からは、「寸止めルール」を採用している道場との相性が良いです。
もっとも、日本国内では競技「形」は、第一指定型(8種)と、第二指定型(8種)から、それぞれ選択して行うのに対して、オリンピックルールの採用する世界空手連盟競技規則では演舞可能な形が75種類あります。
今後、全空連が積極的にオリンピックルールに基づいた指導を増加させていくと思われますが、現状では、お子さんの教室選びや、ご自身が習いたい空手教室の参加にあたっては、オリンピックルールを積極的に採用しているかどうかは、参考程度にとどめておくのがよいでしょう。
空手の流派にはどんなものがあるの?
空手には多くの流派があります。
ここでは、一般的に主要と言われており、「寸止めルール」を採用している「四大流派」と、現在の空手に大きな影響を与えた「フルコンタクト空手」を採用している「全日本空手道練武会」と「極真会館」について紹介します。
四大流派 松濤館流
松濤館流は、空手を日本全土に認知させた1922年(大正11年)体育展覧会、講道館演舞を実施した船越義珍を創始者とする流派で、最も歴史ある流派です。>
船越義珍は、仏教思想の「色即是空」「空即是色」から、「からて」の漢字表記を「空手」と命名し、普及に努めたとされています。
元来、沖縄県女子尋常小学校の教師であったこともあり、教育熱心であり、「道場訓」「松濤二十訓」などの訓示、「琉球拳法唐手」「練胆護身空手術」「空手道教範」など数多くの著作も残しています。
全空連では、第一指定形として、ジオン、カンクウダイ、第二指定形として、エンピ(燕飛)、カンクウショウ(観空小)が採用されています。
昭和23年に設立公益社団法人日本空手協会が設立され、現在では総本部道場、9の地区本部、47都道府県の本部道場を擁する団体です。
早期から指導体制の確立に力を入れている団体ですので、全国レベルで一定の指導水準ができる体制にある数少ない流派です。
参考までに、2020年東京オリンピックの主要開催団体である全空連以外、公益法人の認定を受けているものは、松濤館流の日本空手協会のみです。
四大流派 剛柔流
沖縄出身の宮城長順が、沖縄と中国で習得した武術を体系化したものとされています。
1934年に大日本武徳会(戦前の組織)に「剛柔流唐手」と記載されており、その頃には流派として成立していたと考えられ、松濤館流に次いで古い流派です。
沖縄での活動が活発だったためか、他の流派には見られない型が多いと指摘されることがあります。
全空連では、第一指定形として、セーパイ、サイファ、第二指定形として、セイサン(十三手)、クルルンファー(久留頓破)が採用されています。
現在でも、全体として組織化する傾向は強くないようで、沖縄で活動した弟子と、本土で活動した弟子とに分かれた経緯があり、分派が多く存在しています。
なお、後述する「極真会館」を創設した、大山倍達も、もとは剛柔流で空手を習っていました。
四大流派 糸東流
1934年、大阪で摩文仁賢和が開設した「養秀館」道場から続く一派です。
摩文仁賢和は、沖縄で存在していた当時の二流派(首里手、那覇手)を糸洲安恒、東恩納寛量の両名から習ったことから、それぞれの師匠から一字ずつをとり、糸東流と命名しました。
創始者である摩文仁賢和は琉球由来の空手にとどまらず、本土の柔術も積極的に取り入れたため、徒手空拳による打撃を主体としつつも、棒術や投げ技も体系に含んでいる点が特徴的です。
全空連では、第一指定形として、バッサイダイ、セイエンチン、第二指定形として、マツムラローハイ(松村ローハイ)、ニーハイポ(二十八歩)、が採用されています。
琉球由来の武術と、日本本土の武術とが融合している点、柔術の要素が含まれている点などが特徴的です。
日本では全日本空手道連盟糸東会が主要な団体として活動しています。
世界各地に流派を擁している点も特徴的です。
四大流派 和道流
四大流派の中で最も新しい創始者を持つのが和道流です。
創始者は大塚博紀で、松濤流の船越義珍、糸東流の摩文仁賢和をはじめ、本土柔術、柳生新陰流などの古流剣術も習熟した上で和道流を開設しました。
和道流の技術体系は柔術にも及んでおり、一部の技術体系は、和道流柔術拳法として、日本古武道協会の加盟団体として存続しています。
全空連では、第一指定形として、セイシャン、チントウ、第二指定形として、クーシャンクー、ニーセーシー、が採用されています。
和同会は、技術体系が剣術にまで含んでいる点や、師範が代々、大塚博紀の名称を襲名している点も特徴的な流派です。
戦前のフルコンタクト空手
前述したように、全空連は「寸止めルール」を採用しています。
これは、強打ではない打撃をポイントとして評価し、勝敗の判定を行うものであり、相手を負傷させる強打は反則行為として失格となります。
これに対して、いわゆる「フルコンタクト」ルールでは、股間や目など極めて危険な箇所への攻撃を除き、相手への強打を認め、ノックアウトさせる強打を認めます。
あまり知られていませんが、防具付きでのフルコンタクトを行う流派も存在します。
1959年に、遠山寛賢、玉得博康らが主体となって立ち上げた、全日本空手道連盟は防具付きのフルコンタクト空手を採用していましたが、各流派の合意を得るまでには至らず、解散しました。
フルフェイスマスクなど防具の安全性技術が高まったこともあり、現在は、全空連の協力団体として全日本空手道連盟錬武会が活動を行っています。
戦後のフルコンタクト空手 極真会館
「フルコンタクト」のルールを採用した団体で最も有名なのが、「極真会館」です。
四大流派のひとつである剛柔流を学んだ大山倍達は、1954年、ほぼ全ての打撃を認める日本空手道極真会大山道場を設立しました。
当初のルールは非常に過激で、目つきや股間蹴りまでも認めるというものでした。
大山道場はその後、国際空手道連盟極真会館へと改称し、多くの大会を開催していく中で徐々に競技規則で危険な技は禁止され、現在に至っています。
現在、極真会館の採用するルールは「極真ルール」といわれ、目つき、股間蹴り、顔面への手拳の攻撃は禁止されていますが、素手で競技を行うという点に特色が残っています。
1994年に大山倍達が死去し、「極真会館」そのものも分裂の危機を迎えましたが、松井章圭が後を引き継ぎ、現在でも「国際空手道連盟極真会館」の会員数は1200万人を超えています。
大山倍達は「寸止めルール」に対して一貫して反対していました。
極真会館はメディアへの露出も多く、キックボクシングや総合格闘技へ強い影響を与えてきました。
大山倍達亡き後、かつては全空連とは距離を置いていたフルコンタクト団体の多くが、寸止めルールの空手がオリンピックに採用されてから、徐々に全空連にすり寄るする関係になっています。
より実践を追求する空手団体からは、「武道の信念がない」と揶揄されてもいます。
もっと詳しく知りたい人に
以上に空手の流派について、「空手」がどのように生まれたのかを簡単にふまえつつ、駆け足で説明をいたしました。
より詳しく知りたい場合は、まずは「公益財団法人全日本空手道連盟」のサイトを見てみましょう。
また、英語のウェブサイトしかありませんが、世界空手連盟(WKF)のウェブサイトを参照されると、世界における「空手」の受け取り方が把握できるかと思います。
参考リンク:(主要なもの)
世界空手連盟:https://www.wkf.net/
世界空手連盟競技規則:https://www.wkf.net/pdf/competition_rules_version9_2015_en1.pdf
オリンピックルール:https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/games-olympics/karate/index.html